内乱の一世紀、終わりの始まり
歴史作家、塩野七生による大長編『ローマ人の物語』(新潮文庫)全43巻を紹介していくこのコーナー。前巻ではついに、ガイウス・ユリウス・カエサル(B.C.100~B.C.44)が軍団を率いてルビコン川を渡り、共和政ローマと元老院に反旗を翻しました。 今回ご紹介する『ローマ人の物語(11)ユリウス・カエサル ルビコン以後(上)』(新潮文庫)では、カエサルによるルビコン渡河直後から、彼のローマ本国制圧、そしてかつての盟友グナエウス・ポンペイウス(B.C.106~B.C.48)との対決までが描かれます。B.C.133年から長きに渡って続いてきた「内乱の一世紀」も、終盤に差し掛かってきました。

ローマ人の物語 (11) ユリウス・カエサル ルビコン以後(上) (新潮文庫)
- 作者: 塩野七生
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 2004/09/29
- メディア: 文庫
- 購入: 2人 クリック: 10回
- この商品を含むブログ (92件) を見る
得意の速攻でローマ本国制圧
「賽は投げられた!」の名言と共に、共和政ローマ本国の北の国境であったルビコン川を越えたカエサルは、得意の速攻で次々に都市を制圧していきました。ガリアを平定した英雄カエサルを、一般市民たちが熱狂を持って迎えたこともあり、彼は完全に主導権を握ります。
この報を受け、首都ローマの元老院派は浮足立ちました。彼らに担がれてカエサルと戦うことになったポンペイウスも、首都の放棄を決定します。
ただ、「ローマ最高の軍司令官」とまで呼ばれたポンペイウスがこうも簡単に首都を放棄したのには、合理的な理由がありました。元々首都ローマには、軍事クーデターを防ぐため、最小限の軍事力しか置かれていません。ポンペイウスも、これではとてもカエサルに対抗できないと判断したのです。
ポンペイウスは首都、そしてローマ本国までも放棄し、外地で反撃の機会を窺うことになりました。この状況に、反カエサルを掲げていた元老院議員たちも、恐れをなして逃げ出します。
カエサルには反対派を粛正するつもりなど毛頭ありませんでしたが、30~40年前に行われたガイウス・マリウス(B.C.157~B.C.86)やルキウス・コルネリウス・スッラ(B.C.138~B.C.78)による大虐殺は、未だ多くの人の記憶に残っていたのでしょう。
ポンペイウス、依然強勢を誇る
ローマ本国を追われたとはいえ、ポンペイウスには依然として、カエサルに対抗しうる力が残っていました。むしろ、その勢力範囲を見れば、ポンペイウスの方が断然有利であったと言えます。
カエサルが地盤としたのは、自ら平定したばかりのガリア(現フランス)とローマ本国(現イタリア)です。これに対しポンペイウスは、カエサルを包囲するように、ヒスパニア(現スペイン)、北アフリカ、エジプト、パレスティナ、シリア、小アジア(現トルコ)、ギリシアを勢力圏としていました。
興味深いのは、この状況下でも、平定間も無いガリアでカエサルに反旗を翻そうという動きが微塵も見られなかったことです。もしカエサルがガリア平定の折に禍根を残していれば、彼がポンペイウスを相手取らねばならなくなった時点で、ガリアが反カエサルに立ち上がる可能性もあったはず。しかし、それが全く起こらなかったという事実は、カエサルの戦後処理がいかに見事であったかを示しています。
カエサル、ドゥラキウムにて大敗
この包囲網を突破し、ポンペイウスの足場を崩すべく、西へと軍を進めたカエサルは、ヒスパニアに駐留していたポンペイウス側の軍団と戦い、この解体に成功。配下の将に任せていた北アフリカ戦線では手痛い敗北を喫しますが、最終的にはギリシアでポンペイウス本人と対峙することになりました。
ただ、今度の相手はローマ一の将軍と謳われたポンペイウスです。そう簡単に事は運びません。カエサル軍の上陸こそ許したポンペイウスでしたが、ギリシア北部西岸、アドリア海に面したドゥラキウムの地に陣を敷き、カエサルを迎え撃ちました。
カエサルはこれを包囲しましたが、ポンペイウス指揮下の兵力4万5000人に対して、カエサルが率いるのは1万5000人。元々3倍の兵力差がある相手を外側から囲もうという方に無理がありました。海を背にしている大軍が相手ですから、補給を断つ戦術も考えられましたが、あいにく制海権もポンペイウスに握られているという状況です。
丘を取り合う攻防戦の末、弱点である南側を破られたカエサル軍は敗走。カエサル自身、危うく命を落としかけるほどの敗北でしたが、兵力の実害としては1000人ほどであったため、態勢を立て直して、再びポンペイウスに挑むこととなります。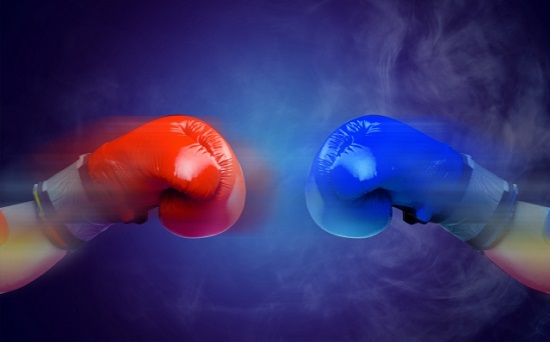
ファルサルス決戦
ドゥラキウムから逃げるように南下するカエサルと、それを追うポンペイウス。両者はついに、決戦の地ファルサルスにて、再び相対します。
ポンペイウス自身はカエサルの力を侮らず、相手の資金および兵糧の不足を突いた持久戦法を取るべきだと考えましたが、ポンペイウス側の陣営は勝利を確信して即時決戦を主張。総じて浮かれ気分でした。カエサルと戦う上での方針を決めるべき軍議の場で、カエサル亡き後のローマ政界における役職を巡った議論が行われる始末だったと言います。
こうして、戦いの火蓋が切って落とされました。カエサル軍は兵力こそ劣っていましたが、ガリア戦役を経てきた精鋭が揃っており、練度ではポンペイウス軍の比ではありません。指揮系統の乱れが目立ったポンペイウス側は戦線が崩壊。ポンペイウスを含む一部を将を除き、元老院派に属していた多くの有力者はカエサルの手に落ちました。
ポンペイウスの死とエジプト平定
ローマ内戦中最大の激戦と言われたファルサルスの戦いに勝利を収めた後、カエサルは逃走したポンペイウスを追ってエジプト王国の首都アレクサンドリアへと向かいました。しかし、そこで彼にもたらされたのは、ポンペイウス暗殺の報でした。
当時のエジプトには、不穏な空気が漂っていました。姉弟であり夫婦でもあったクレオパトラ7世(B.C.69~B.C.30)とプトレマイオス13世(B.C.63~B.C.47)が、共和政ローマとの距離感を巡って対立を深め、戦闘状態にあったのです。
クレオパトラ7世が、強大なローマとの同盟維持こそ国家安泰に繋がると考えたのに対し、プトレマイオス13世は、ローマからの独立を主張しました。そして、このプトレマイオス13世こそ、ポンペイウス殺害を命じた張本人でした。
カエサルの「敵」であったポンペイウスを葬ったことで、プトレマイオス13世はカエサルに貸しを作ったつもりでいました。しかし、たとえ一時的に敵であっても、自国民の、しかもポンペイウスほどの超有力な公人の生殺与奪権を他国に委ねる由縁はありません。
特にプトレマイオス13世は、恩義こそあれ、恨みは無いはずのポンペイウスを裏切ったわけですから、カエサルはポンペイウスの同胞として許すわけにはいきませんでした。こうしてカエサルはクレオパトラ7世の側につき、プトレマイオス13世との戦いに勝利。エジプトを平定し、クレオパトラ7世を権力の座に就けます。
カエサルがクレオパトラと組んだ理由
一説によると、「絶世の美女」と謳われるクレオパトラ7世がカエサルを籠絡した結果、2人は個人的関係から政治的にも手を組むに至ったと言います。フランスの哲学者ブレーズ・パスカル(1623~1662)が遺稿集『パンセ』の中で「クレオパトラの鼻がもう少し低かったら、歴史は変わっていた」と書いた所以ですね。
真偽のほどは定かでないとはいえ、「自身の身体を絨毯にくるませ、カサエルの前に姿を現した」という逸話が知られるなど、クレオパトラが美貌と才気でカエサルの心を掴んだことは確かなようです。カエサルも若い頃から女好きでは有名でしたし、異説はありますが、後にプトレマイオス15世となるカエサリオン(B.C.47~B.C.30)も、2人の間に生まれた子だと言われています。
それでも、カエサルの政治的判断におけるクレオパトラの影響力は、決して大きなものではなかったでしょう。カエサルは立派な公人であり、ローマの代表者です。その一挙手一投足にローマ市民の目が注がれています。今後、権力者としてローマの政治を握っていくにあたって、ローマ人として相応しい行動を取らねばならない立場にありました。
カエサルは、ポンペイウスの死の報に際して涙を流したと伝えられますし、義理人情を解する人間であったことは間違いありません。クレオパトラに魅力を感じたのも事実でしょう。
しかし、そうした個人的な感情とは別の論理で、ローマ市民に相応しい行動として取られた選択が、同胞であるローマ人を殺害したプトレマイオス13世への攻撃であり、親ローマを貫いてきたクレオパトラ7世との同盟であったと考えられます。カエサルはあくまで、冷徹なまでに現実主義の政治家でしたからね。
いずれにせよ、カエサルにとって最大のライバルがこの世からいなくなったことに変わりはありません。こうしてローマ唯一の権力者となった彼は、自ら思い描いてきた国家体制の改造に向けて辣腕を振るうことになります。
(次巻へつづく)